
住まい探しをするとき、間取りや設備といった住宅のスペックや特徴を考えることも大切ですが、それよりも前に「どこに住むか」を決める必要があります。ライフスタイルや家族構成をもとに最適な住む場所を探されると思いますが、実際に安心して快適な日々を送ることができるか、住み始めてから不便に感じたり、悩みを抱えたりしてしまうのか、事前にどこまでわかるものなのか不安がありますよね。 住む場所で後悔しないために、この記事ではどのような観点から住む場所を決めればよいのか、ポイントを解説します。
目次
1.住む場所を決めるために重視されていることは?
2.住む場所を決めるための5つのポイント
3.住む場所の決め方 まとめ
住む場所を決めるために重視されていることは?

国土交通省の、令和5年度「土地問題に関する国民の意識調査(P14)」によると、住まいの立地に対して最も重視することのTOP5は「日常の買い物など、生活の利便性が高いこと」が最多で27.0%、「住み慣れた場所であること」18.0%、「治安が良いこと」13.9%、「駅などの公共交通施設に近いこと」11.0%、「自然災害に対し安全であること」6.1%という結果が出ています。また、「職 場 に 近 く 、 通 勤 時 間 が 短 い こ と」が5.5%、「通 学 に 便 利 で あ る こ と」1.5%で合わせて7.0%となり、通勤・通学の利便性も重要視されています。
令和2年~4年の結果と比較して、最新の調査では「住み慣れた場所であること」の割合が大きく減少し、「治安が良いこと」の割合が増加しています。安心して暮らせる環境に重点を置いている人が増加していると考えられます。
住む場所を決めるための5つのポイント
住み慣れた場所に住み続ける方以外は、家探しと同時に新たな住む場所を決めなければなりません。住む場所を決めるためにどのようなポイントをチェックしたらよいのか、順に見ていきましょう。
住む場所を決めるポイント1―生活の利便性

商業施設やスーパーなど日常の買い物スポットまでの距離はどのくらいか、大型の医療機関や通いやすいクリニックは近くにあるのか、子どもを遊ばせやすい公園やレジャー施設はあるか、市役所や図書館など公共施設はどこにあるのかなど、事前に確認をしておきましょう。帰宅時間が遅い場合は営業時間も重要です。家族構成やライフスタイルに合わせてどのような施設があると便利か想定しながら住む場所を決めることで、毎日の生活がしやすくなります。
住む場所の決め方2―治安のよさ

小さな子どもがいるファミリー世帯はもちろん、夫婦や単身者の場合でも、できるだけ治安のよいところに住みたいと考えるのは当然のことです。警視庁が発表している地域ごとの犯罪件数などを確認し、安心して生活ができそうなエリアを選びましょう。
最寄り駅や学校など、頻繁に行き来する場所への経路を確認することも大切です。防犯カメラが設置されているか、死角になりやすいところはないか、交番が近くにあるか、夜間の移動が多い場合は街灯の数や明るさも確認しておきたいところです。下見の際は、昼間と夜間の両方を確認しましょう。繁華街に近いエリアを検討している場合は、口コミ情報なども含めて入念にチェックしましょう。
住む場所の決め方3―公共交通機関との距離感

一般的に、駅などの公共交通施設に近い場所ほど、土地価格や住宅価格は上がります。コストを抑えるために駅から離れた場所に住むことを選ぶ方も多いと思いますが、どこへ行くにも移動に時間がかかるとなれば、日常の移動がストレスになりかねません。 一方で、駅周辺は繁華街を形成していることが多く、近すぎると混雑や騒音が気になることもあります。「幹線道路に面していて車の走行音が気になる」「ごみごみとした街並みが苦手」という方であれば、敢えて最寄り駅から離れ、閑静な住宅街に住むことを選んだ方が快適に過ごせるでしょう。公園などが近く、自然が豊かな場所に住みたい方も同様です。
住む場所を決めるポイント4―通勤・通学のしやすさ

勤務先や学校など、住む場所から日常的に移動する場所へのアクセス環境は重要です。最寄り駅から利用できる路線や運行本数、始発電車の有無といった基本情報をチェックするとともに、ラッシュ時間帯に通勤・通学をする必要がある場合は混雑状況も事前に知っておきたい情報です。合わせて、最寄り駅までの距離はどのくらいで、徒歩や自転車、バスで何分くらいかかるのか、自転車であれば駅前に利用可能な駐輪場があるかや坂道の有無、バスであれば利用時間帯の本数なども考慮したうえで、無理なく通勤・通学ができそうか検討しましょう。
住む場所の決め方5―自然災害リスク
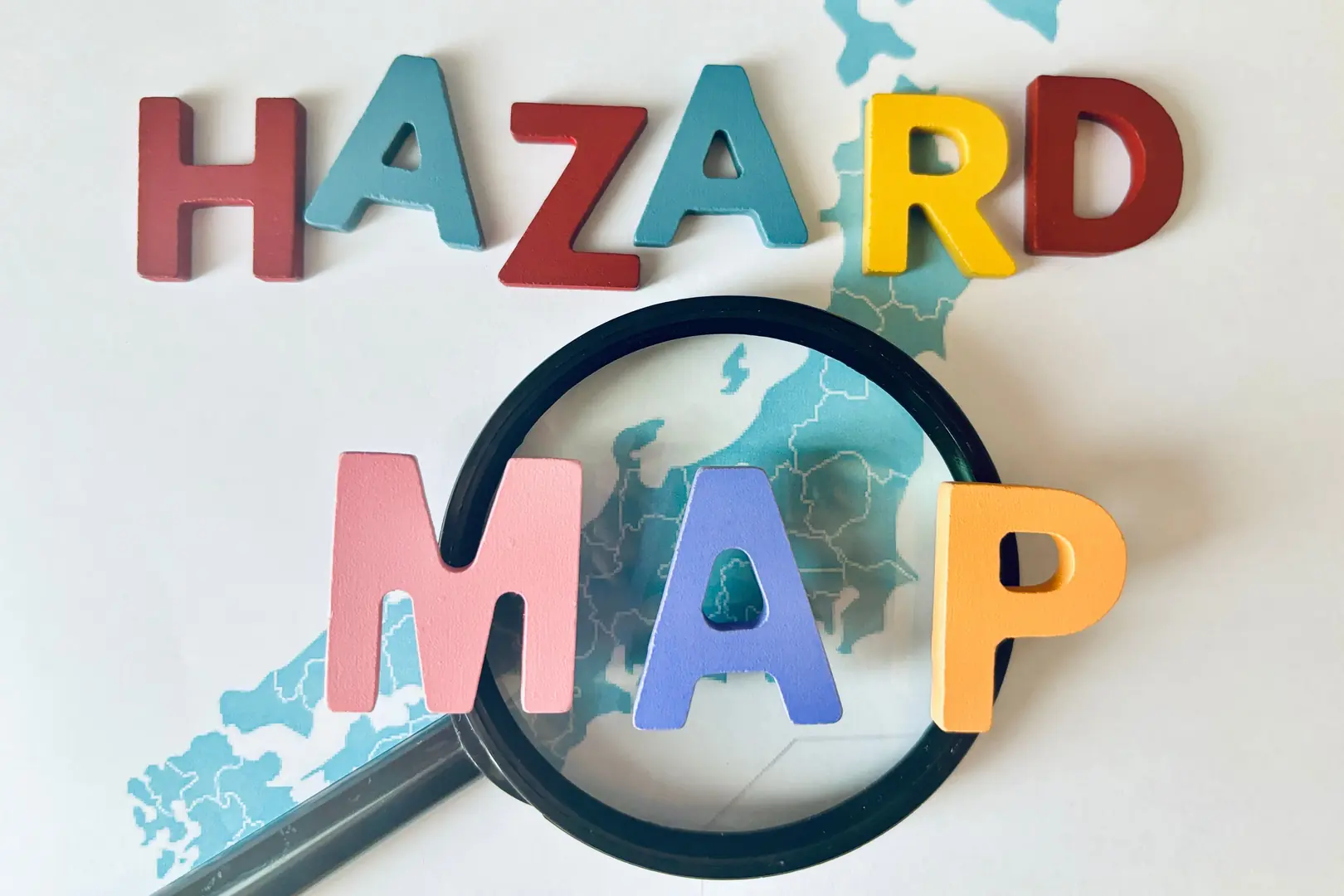
災害大国日本では、地震や台風、洪水、津波、土砂災害、液状化など、さまざまな災害が発生する可能性があります。住みたい場所にどのような自然災害のリスクがあるのか、事前に確認をして対策を講じることが重要です。自治体や気象庁などが提供している災害情報や、災害履歴などの情報をもとに作成される「ハザードマップ」をチェックしましょう。ハザードマップを見れば、浸水しやすいエリアや土砂災害のリスク、津波や高潮のリスク、地震による被害程度の予測や液状化現象のリスクなども知ることができます。
災害リスクを事前に把握することで、家を建てるときにリスクを軽減するための対策をしたり、火災保険や地震保険の加入時に補償を手厚く設定したりすることができます。もちろん、災害リスクが低いエリアを選ぶ際にも重要な情報です。
住む場所の決め方 まとめ
住む場所の決め方について、今回は多くの人が重視している主な5つのポイントを紹介しました。このほかにも、例えば子育て世帯であれば、実家と行き来しやすいかを重視する方や、自治体の支援制度が手厚いエリアを選びたい方、特定の学区内にこだわる方もいるでしょう。10年、20年先のライフステージを見据えて住む場所に求める優先順位を明らかにすることで、自分たちに合った住む場所を見つけましょう。

ラジオパーソナリティを経てフリーライターに。
住宅・インテリア・不動産分野を中心として、介護・グルメ・トラベルなどのジャンルでも執筆。
リフォームや注文住宅関連の住宅情報誌をはじめ、雑誌、書籍、新聞、インターネットなどのさまざまな媒体で取材・執筆を手掛けている。
新築一戸建て注文住宅購入者へのインタビュー記事はこちら







